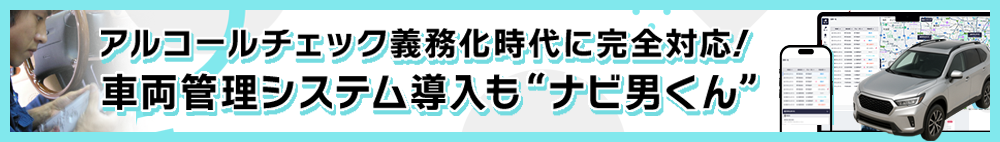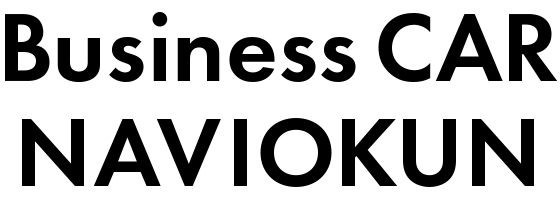2023~2025年における
道交法・道路運送法改正まとめ
投稿日:2025-09-01
車両を業務に使用する企業にとって、法令の改正は業務運用に大きく関わる問題です。
2021年に発生した重大な飲酒運転事故をきっかけに、2022年~2025年にかけて道路交通法・道路運送法が段階的に改正され、2023年12月には「白ナンバー事業者に対するアルコールチェック義務」が完全施行されました。
本記事では、その法改正の流れと背景、そして今後の企業実務に求められるポイントをわかりやすく整理します。
法改正のきっかけとなった重大事故
2021年6月、千葉県八街市で白ナンバーの社用車による飲酒運転による児童死傷事故が発生。社会的に大きな非難が集まり、政府は業務用車両の管理体制の見直しに着手しました。
その結果、従来は緑ナンバー(営業用)中心だった管理強化が、白ナンバー(自家用)の事業者にも拡大されることとなりました。
道路交通法と道路運送法、それぞれの役割
【道路交通法】
警察庁が管轄。主に「安全運転管理者制度」や「アルコールチェックの実施」など、運転者と企業の安全体制に関する義務を定めます。
・安全運転管理者の選任条件・業務内容
・点呼や健康確認の義務
・アルコールチェック記録の義務と保存期間
【道路運送法】
国土交通省が管轄。主に「運送事業の許可・監査・処分」など、運送事業者全体の法令遵守と体制に関するルールを定めます。
・緑ナンバー・白ナンバーの事業者管理
・点呼記録の形式や確認項目
・違反時の許可取消・車両使用制限などの行政処分
白ナンバー事業者にも同じリスクが
この問題は、日本郵便のように物流・運搬に車両を使用している企業だけの問題ではありません。営業車両であっても5台以上保有していれば、安全運転管理者の選任義務と点呼義務が適用されます。
そして、これを怠ると罰金や行政指導の対象となる場合があります。
また、安全運転管理者の選任や点呼をおこなっていなかった企業で飲酒運転事故が起きた場合、使用者責任や運行供用責任を問われ、社会的信用の失墜はもちろん、損害賠償などに対しても、より厳しく追求されることでしょう。
教訓と対応ポイント
- 点呼は形式ではなく「実態」 書類上は形式を整えても、実際に対面で確認されているかどうかが重要です。管理部門によるモニタリング体制を構築し、記録と現場の整合性を常に確認しましょう。
- 記録の信頼性を高める仕組みが必要 紙やアナログ管理では記録自体の改ざんや記録漏れを防げません。システム化・クラウド化により記録の自動化・ログ化をおこない、証跡を確実に残しましょう。
- 現場との危機感共有が大切 まずは運転者をはじめとする現場スタッフに「実際に発覚した場合、どれほどの悪影響があるのか」を理解してもらいましょう。また運用する台数が少ないほどルーズになりがち。問題が発生する前に「穴」を塞いでいきましょう。
そして今後、社会はますます「やっている」だけでなく、「どう証明するか」が問われる時代へと進んでいくでしょう。
企業規模に関係なく、記録の信頼性を高め、点呼体制を日々チェックし、ミスを防ぐ仕組みを備えることが企業防衛の第一歩です。
“自社は大丈夫”という思い込みこそが最大のリスク。「記録を残す」から「仕組みで守る」へ──今こそ、体制の見直しとクラウド活用による実効的な管理体制の構築が求められています。
アルコールチェックに最適の解決策!
アルコールチェックの義務化により、点呼や記録管理の実効性が強く求められる今、クラリオン「SAFE-DR」は最適の解決策をご用意します。アルコールチェッカー連動で記録を一元管理。日報・月報の自動作成や免許・車両情報の管理まで、紙やExcelでは難しい信頼性と証拠性を実現します。法令対応だけでなく、業務効率の向上にも貢献。「やっている」を「証明できる」体制づくりのお役に立ちます。
詳細はこちら⇒
【参考資料】
・警察庁「安全運転管理者の制度概要」→https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido.pdf
・警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」
→https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html