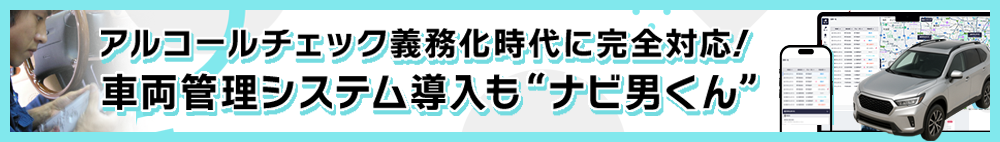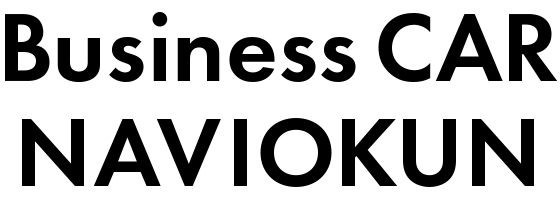日本郵便の事例から考える
事業への影響と企業体制の重要性
投稿日:2025-09-01
2025年3月以降に大きく報じられた日本郵便の点呼不備問題は、アルコールチェック義務の制度自体だけでなく、現場の運用や企業体制がいかに重要かを浮き彫りにしました。
本記事では、違反の内容とその後の行政処分、そしてそこから学ぶべき教訓を整理します。
日本郵便の点呼不備問題とは?
2025年1月下旬、兵庫県の小野郵便局において、点呼が実施されていない状況が確認されました。その後、近畿支社管内140局で不備が発覚し、国交省も監査へと移行しました。
全国調査では、全3,188局のうち約75%(2,391局)で点呼に何らかの不適切事例があり、その総数は計15万1,000件に及ぶことが確認されました。 さらに実際に勤務時間中の飲酒運転事案も発生し、一層の注目と批判を集めることになりました。
【不備内容の具体例】
・点呼を実施したように見せかけて虚偽の記録を作成
・対面ではない場所や適正でない環境で点呼を実施
・健康確認・酒気帯び確認・免許証確認など、必要な確認項目が省略されていた
車両の事業許可取り消しも
国交省は、日本郵便に対し1t以上の車両(約2,500台)の事業許可取り消し(5年間使用不可)の方針を固めました。これは極めて異例かつ重い処分です。
同時に、点呼・アルコールチェックの管理体制そのものの再構築を求める是正命令も発令されました。
白ナンバー事業者にも同じリスクが
この問題は、日本郵便のように物流・運搬に車両を使用している企業だけの問題ではありません。営業車両であっても5台以上保有していれば、安全運転管理者の選任義務と点呼義務が適用されます。
そして、これを怠ると罰金や行政指導の対象となる場合があります。
また、安全運転管理者の選任や点呼をおこなっていなかった企業で飲酒運転事故が起きた場合、使用者責任や運行供用責任を問われ、社会的信用の失墜はもちろん、損害賠償などに対しても、より厳しく追求されることでしょう。
教訓と対応ポイント
- 点呼は形式ではなく「実態」 書類上は形式を整えても、実際に対面で確認されているかどうかが重要です。管理部門によるモニタリング体制を構築し、記録と現場の整合性を常に確認しましょう。
- 記録の信頼性を高める仕組みが必要 紙やアナログ管理では記録自体の改ざんや記録漏れを防げません。システム化・クラウド化により記録の自動化・ログ化をおこない、証跡を確実に残しましょう。
- 現場との危機感共有が大切 まずは運転者をはじめとする現場スタッフに「実際に発覚した場合、どれほどの悪影響があるのか」を理解してもらいましょう。また運用する台数が少ないほどルーズになりがち。問題が発生する前に「穴」を塞いでいきましょう。
制度が整っていても、現場での運用が機能していなければ、それは“形だけ”の対策に過ぎません。そして今後、社会は「やっていること」よりも「どう証明するか」が問われる時代へと進んでいきます。
記録の信頼性を高め、点呼体制を日々チェックし、ミスを防ぐ仕組みを持つことが企業防衛の第一歩です。
“自社は大丈夫”という思い込みこそが最大のリスク。「記録を残す」から「仕組みで守る」へ──今こそ、体制の見直しとシステム化による実効的な管理体制の構築が求められています。
“やっている証拠”を残す体制へ
日本郵便の点呼不備問題が示したのは、「やっていたか」より「証明できるか」が問われる時代の到来です。
クラリオン「SAFE-DR」なら、点呼・アルコールチェック・運転記録をすべてクラウドで自動保存し、改ざん防止と証拠性を両立。ミスや不正の“穴”を塞ぎ、監査・トラブル時も企業を守る仕組みが整います。実態に基づく記録で“形だけ”の対策を脱却し、信頼される管理体制を。車両へのドラレコ取り付けは全国対応の「ナビ男くん」におまかせください。
詳細はこちら⇒
【参考資料】
・日本郵便株式会社「点呼不備事案に係る調査結果及び再発防止策等について」→https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2025/00_honsha/0423_03_02.pdf
・日本郵便株式会社「報告徴求に対する報告書(概要)」
→https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2025/00_honsha/0625_02_02.pdf